時間は過ぎ去る、それでも体験は残る 六本木クロッシング2025展を歩く
「時間」をテーマにした現在地の記録

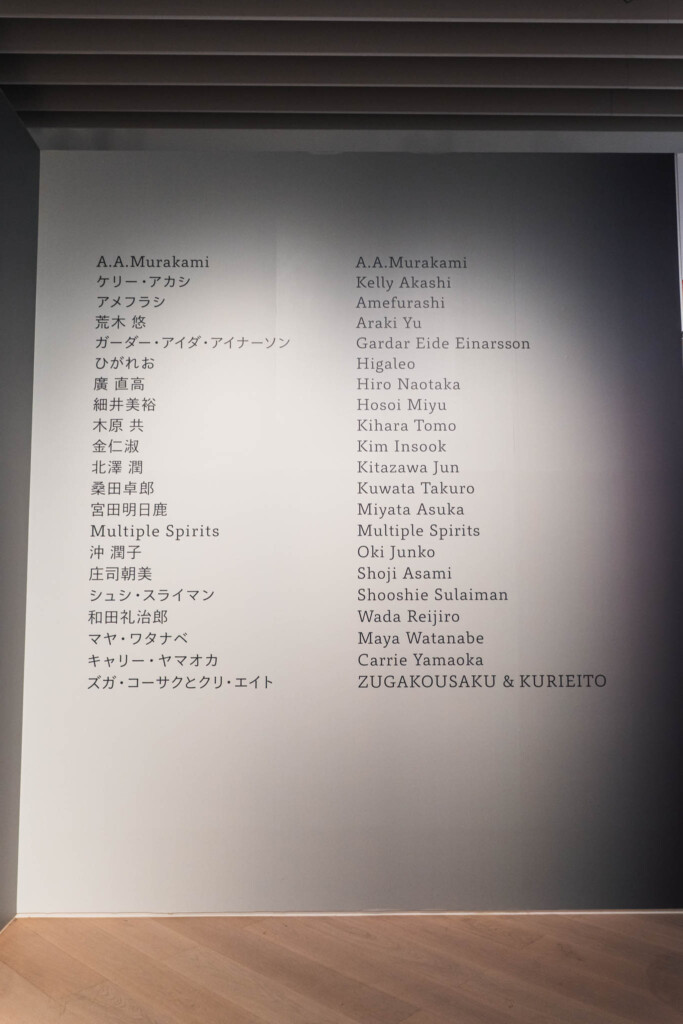

三年に一度、森美術館が開催する「六本木クロッシング」は、その時代における日本の現代美術の“現在地”を定点観測する展覧会として位置づけられてきた。
2025年から2026年にかけて開催されている本展は、その第8回目にあたる。
会場は六本木ヒルズ森タワー53階に位置する 森美術館。
都市の高度と視界の広がりを常に意識させるこの場所は、展示空間でありながら、現実世界との距離感そのものを問い直す装置として機能してきた。






今回のタイトルは
「六本木クロッシング2025:時間は過ぎ去る わたしたちは永遠」。
この副題が示す通り、本展では「時間」が中心的なテーマとして据えられている。ただしそれは、時計や年代史といった直線的な時間ではない。
むしろ、身体感覚としての時間、記憶として沈殿する時間、都市やテクノロジーが内包する時間といった、多層的で不均質な時間が、作品ごとに異なるかたちで立ち上がってくる。
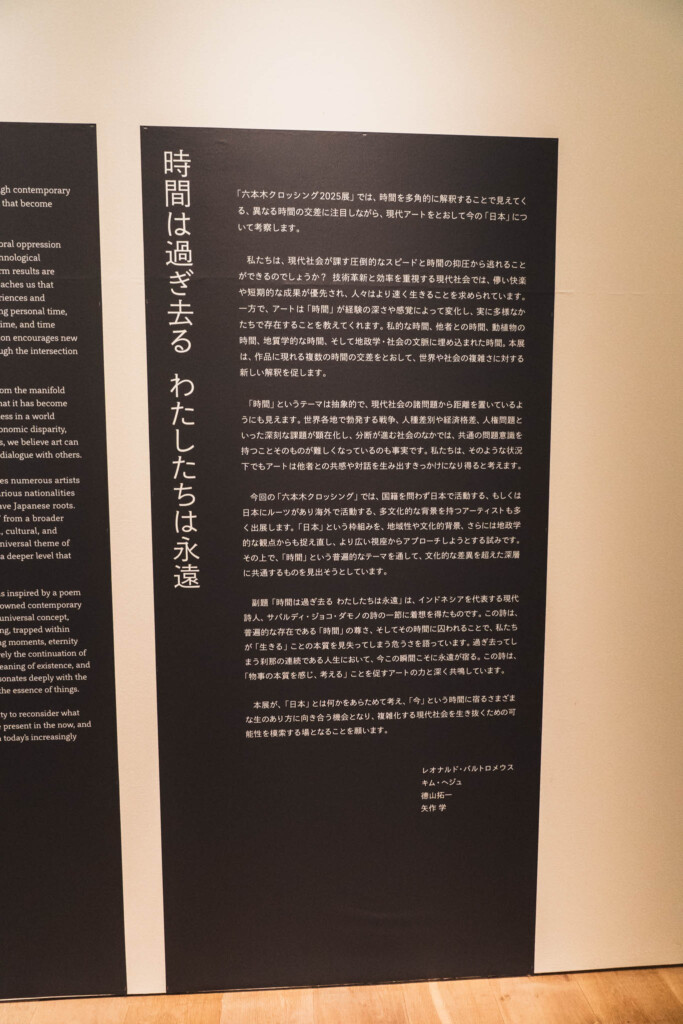










想像以上の混雑が示すもの
私が訪れたのは2026年1月24日(土)の午後。
正直なところ、年明けからしばらく経った時期でもあり、会場はもう少し落ち着いているだろうと予想していた。しかし実際には、展示室の各所で人の流れが滞るほどの混雑が続いていた。
この混雑は、単なる人気展という理由だけでは説明しきれない。
多くの来場者が、作品の前で立ち止まり、スマートフォンやカメラを構え、あるいは何も撮らずに長い時間を過ごしている。その姿から感じられたのは、「いま、この空間でしか成立しない体験」を逃すまいとする切実さだった。
本展の作品群は、即物的なわかりやすさよりも、体験に時間を要するものが多い。
結果として、鑑賞者一人ひとりの滞在時間が長くなり、会場全体に“時間が溜まる”ような状態が生まれていた。








六本木クロッシングというフォーマットの成熟
「六本木クロッシング」は、若手作家の発掘展として語られることが多いが、近年は単なる登竜門的役割を超え、同時代の感覚を編み直す場へと変化している。
今回参加している作家たちは、いずれもメディアや手法が大きく異なる。
インスタレーション、彫刻、映像、写真、パフォーマンス、そして都市空間を扱う実践まで、その幅は非常に広い。
にもかかわらず、展示全体に一貫して感じられるのは、
「制作のスピードをあえて落とすこと」への意識だ。
即時性や拡散性が当たり前となった現代において、ここに並ぶ作品の多くは、鑑賞者に“立ち止まる時間”を要求する。
それは反時代的でありながら、いま最も切実な態度でもある。





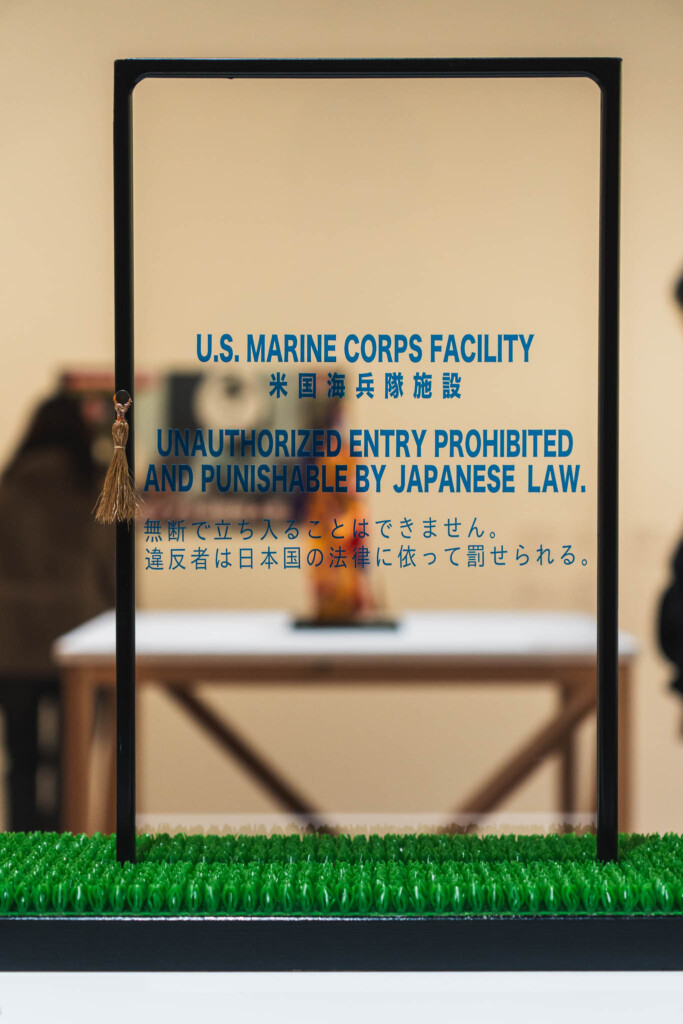






A.A. Murakami《水中の月》(2025)
儚さが循環する時間のインスタレーション
暗室に足を踏み入れた瞬間、感覚は一気に日常から切り離される。
A.A. Murakamiの《水中の月》(2025)は、霧、シャボン玉、プラズマといった要素を精緻に制御しながら、消えていくことそのものを主題化したインスタレーションだ。
暗がりの中で生成され、落下し、水面で弾けるシャボン玉。その一つひとつは極めて短命だが、同時に絶えず生成され続けることで、空間全体には不思議な持続感が生まれている。
私はこの作品の前で、何度もカメラの設定を変えながら撮影を繰り返した。
シャッタースピードを変えるたびに、同じ現象がまったく異なる像として写り込む。その体験自体が、この作品の核心なのだと思う。
《水中の月》は、時間を「測る」ものではなく、時間が感覚にどのように作用するかを静かに問いかけてくる。




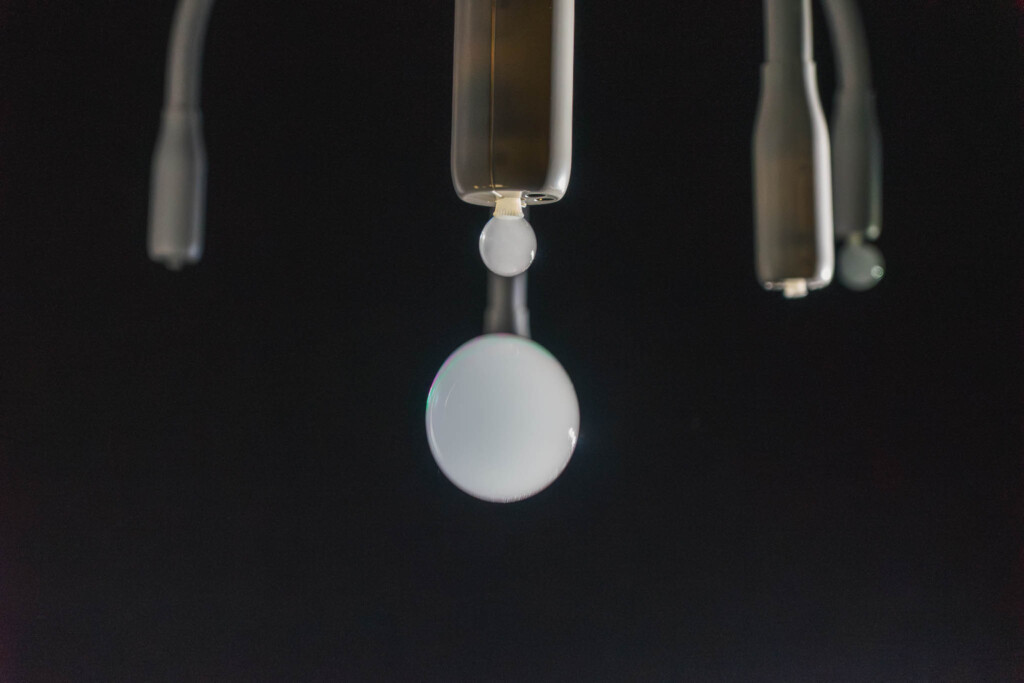

和田礼治郎《MITTAG》(2025)
光と都市がつくる、変化し続ける彫刻
森美術館の展示空間の中でも、私が特に好きな“あの場所”。
和田礼治郎の《MITTAG》(2025)は、外の景色を取り込みながら成立する作品であり、その意味でこの美術館の立地と切り離せない。
ガラスと液体、そして都市の光。
太陽の角度が変わるにつれ、作品の表情もまた刻々と変化していく。
私は時間帯を分けてこの作品を訪れ、その移ろいを写真に収めた。
昼の強い光、傾き始めた午後、夕刻の柔らかな色。それぞれがまったく異なる作品体験をもたらす。
《MITTAG》は、完成された“物”ではなく、時間とともに生成され続ける状態そのものなのだ。









ズガ・コーサク+クリ・エイト
段ボールで再構築された六本木という都市
段ボールやパッケージ素材によって再現された六本木の街並み。
ズガ・コーサク+クリ・エイトの作品は、一見すると模型のようでありながら、強烈な現実感を伴って迫ってくる。
素材は軽く、仮設的で、いかにも壊れやすい。
しかしその脆さこそが、都市が積み重ねてきた時間の層を逆説的に浮かび上がらせる。
六本木という街が、再開発と更新を繰り返してきた場所であること。
その「仮の状態」が、段ボールという素材によって極めて的確に表現されている。






「時間は過ぎ去る、わたしたちは永遠」──その意味
本展を通して感じたのは、「永遠」という言葉が、固定された何かを指していないということだ。
むしろ、過ぎ去り続ける時間の中で、何が残り、何が循環するのか。その問いこそが、作品群を貫いている。



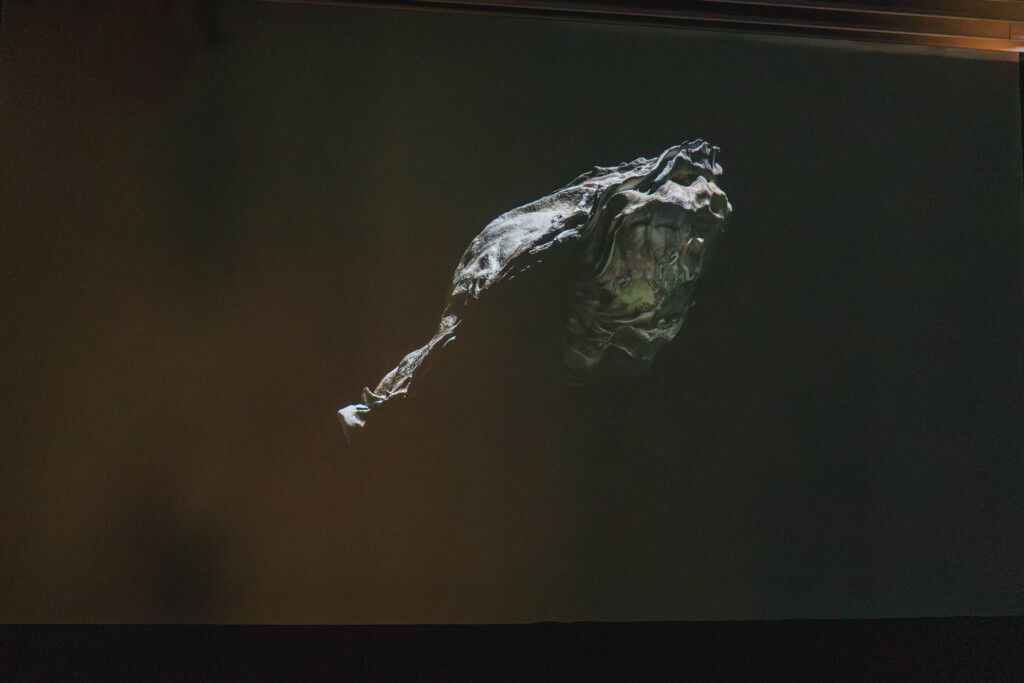
混雑した会場で立ち止まり、待ち、見つめ、時には何も起こらない時間を過ごす。
その体験そのものが、この展覧会の一部なのだと思う。
六本木クロッシング2025展は、
「いま、この瞬間に立ち会っている」という感覚を、静かに、しかし確実に刻み込む展覧会だった。















この記事へのコメントはありません。