大宮エリー 回顧展「生きているということ」創作と生の軌跡を訪ねて
2025年11月23日、私は東京都内で開催されていた 大宮エリー の回顧展「生きているということ」を巡った。会場は三か所。始まりは港区・六本木、次に代官山、そして最後に三宿・池尻。
この展覧会は、彼女が 2025年4月にこの世を去り、50歳の誕生日となる11月21日から始められたもの。生涯にわたって残した 絵画・写真・陶器・書籍など1269点 の作品から選ばれたものが、各会場で展示されている。
足を運ぶごとに、まるで彼女の人生を辿る旅 回顧と再会と別れの、静かな巡礼だった。



■ 回顧展の全体構成と背景
展示は、三つのギャラリーによって構成されている。
- 小山登美夫ギャラリー(六本木)
- DAIKANYAMA GARAGE(代官山)
- CAPSULE(池尻/三宿)
それぞれが、彼女の多面性と創作の広がりを丁寧にたどる役割を担っていた。
六本木は画家としての彼女の足跡を追う精選された絵画とドローイング。
代官山は大型絵画、写真、書籍、絵本原画、VR映画「周波数」の上映など、多角的な創作を網羅。
池尻では、遺作となった襖絵や陶器作品を屏風として展示。
彼女が生前「誕生日に東京でお披露目したい」と語っていた思いを、オーナーが実現させた場所でもある。
会場によっては、展示作品は販売もされており、書籍・グッズの購入も可能だった。
単なる「追悼展」ではなく、
生きることそのものを体現する展示構成。
それが今回の展覧会の大きな特徴だった。


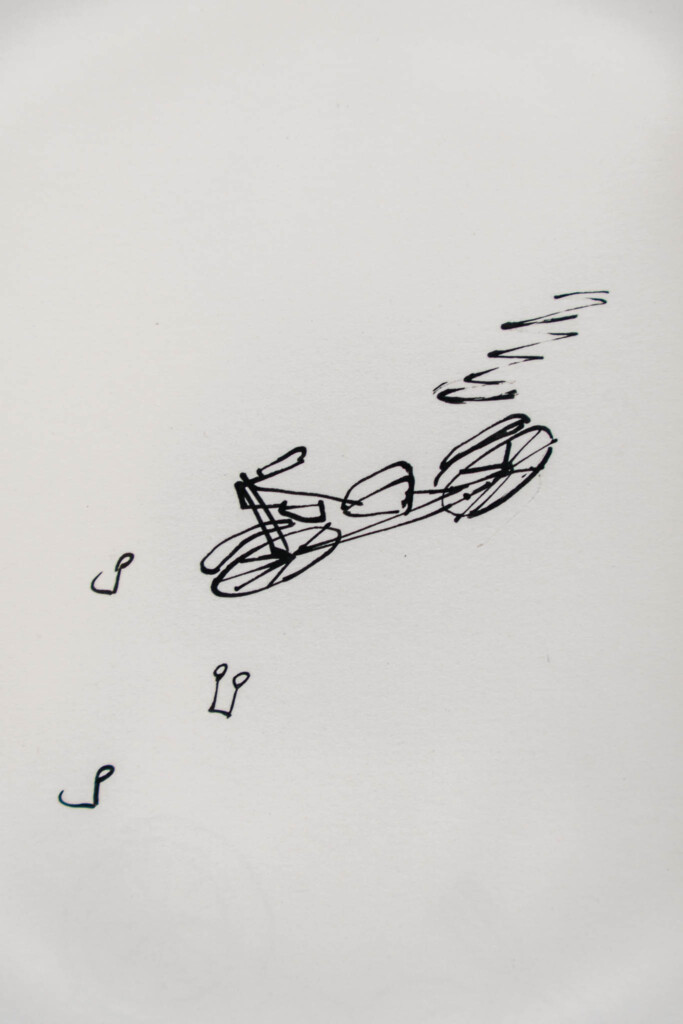
■ 六本木:画家としての始まりとその軌跡
六本木のギャラリーでは、2012年の画家デビュー以降、晩年までの絵画・ドローイングが並んでいた。
目に飛び込んでくるのは、明るく自由な色彩と穏やかな筆致。
ある作品には「珊瑚礁と青い魚たちⅠ」というタイトルが付けられており、海や自然に対するまなざし、透明感が感じられた。
多くの作品が“新作発表”という形ではなく、
生活の記録として、日記のように積み重ねられている。
作品と作品の間に “間” があり、余白がある。
その余白に、迷いや、希望や、呼吸が宿っている。
観覧者は静かに、あるいは立ち止まり、
ゆっくりと作品と向き合っていた。
その姿は、作品に「敬意」を払うというより、
どこかで再会しているような、微かな懐かしさを伴っていた。


















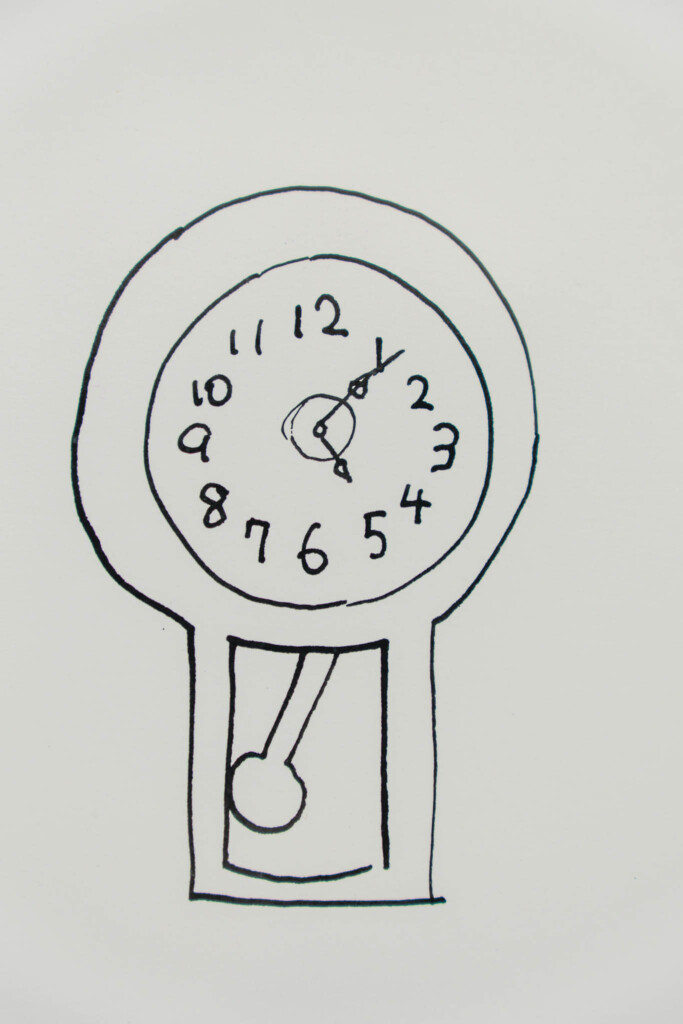

■ 代官山:創造の広がりと “日常” の豊穣
代官山会場 DAIKANYAMA GARAGE。
ここは「創作の広場」のように感じられた。
1階には約30点の大型絵画が並び、
階段をのぼった先には、彼女の「部屋」を再現した空間。
書棚には、彼女が生前に刊行した39冊の本、絵本の原画、写真資料。
言葉とイラストが並んでいるだけなのに、呼吸の温度が伝わる。
階段には動物のオブジェが飾られ、
ほんの少し遊び心がある。
見落としそうな日常の輝き
それがそのまま作品になっている。
奥では、VR映画『周波数』が上映されていた。
目の前で触れられないのに、
すぐそばにあるような感覚。
映像作品では、彼女の世界観を追体験できた。
静けさと創造の躍動が共存する会場だった。
そこにいたのは作品だけではなく、
その生きた時間そのものだった。


































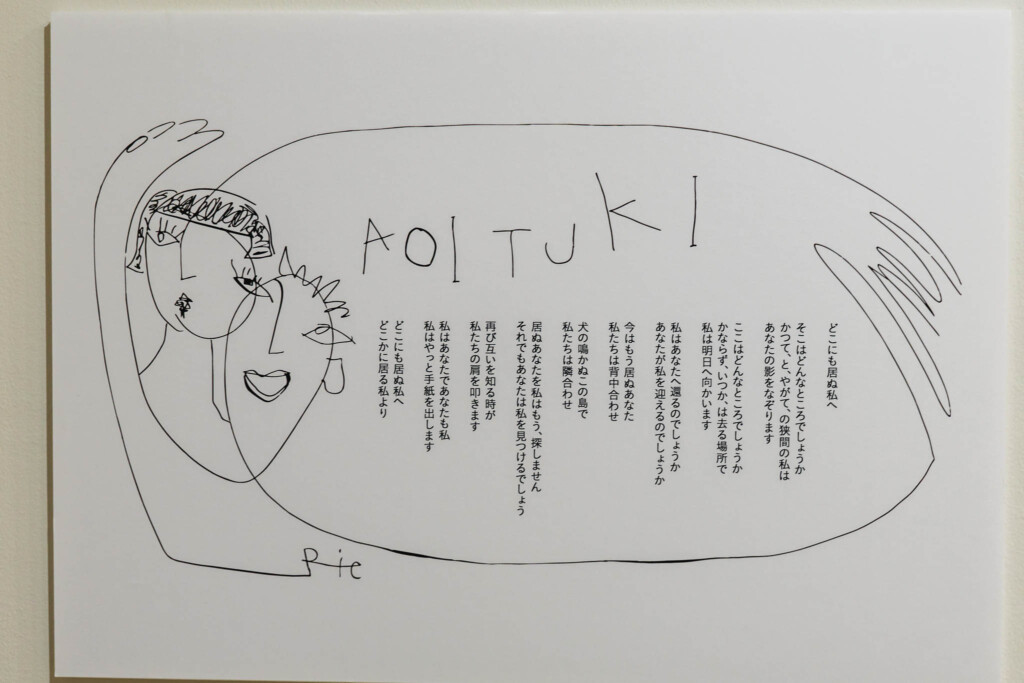


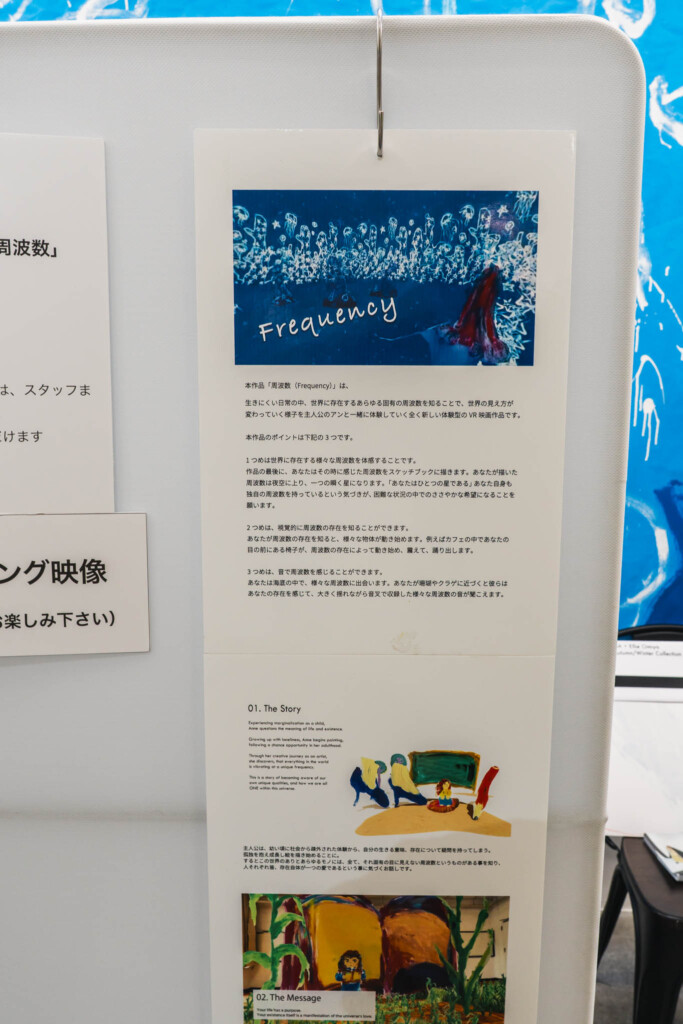


■ 池尻(CAPSULE):赤の祝祭、そして遺作との対話
三宿にある地下のギャラリー・CAPSULE。
階段を降りてドアを開けると、まず 赤い絨毯 が広がっていた。
靴を脱ぎ、一歩を踏み入れる。
その瞬間、外の空気はすっと遠ざかり、別世界へ誘われる。
中央には、屏風作品。
かつて京都で展示された襖絵と陶器を組み合わせ、
屏風として生まれ変わったもの。
ピンクや赤、花や植物、器、動物。
色は鮮やかで、生命感に満ちているのに、
どこか静かで、落ち着いた気配が漂っていた。
陶器の作品がそっと並び、
空間全体が “生と祈りと記憶の場” になっていた。
その場に立つと、悲しみが重くのしかかるのではなく、
むしろ、やわらかく、あたたかい。
「ここにいた人」の残り香が静かに漂っていた。
展示であり、記念であり、
そして、静かな “再会の場” でもあった。









■ 展覧会を巡って感じたこと
三つの会場をめぐりながら、作品の前に立つたびに、
感じられたのは「お別れ」よりも、むしろ 出会い直し に近い感覚だった。
絵画や陶器だけでなく、
言葉や写真、部屋の佇まいまで含めて、
作品は今も呼吸している。
明るさ、楽しさ、ユーモア、そして、ごく小さな哀しみ。
それらはどれも、ひとつの人生の断片であり、
今も続いているもののように感じられた。
会場を後にする時、胸に残ったのは喪失ではなく、
不思議なあたたかさだった。
展示を見たというより、
ひとりの人の歩んだ道を、静かに同行したような気持ちだった。


■ 最後に:色彩の向こうに、ひとつの「生き方」があった
深刻になり過ぎず、
軽やかだけれど、浅くはない。
それが彼女の作品の魅力だった。
今回の三つの会場は、
美術館というより「生活の延長」にあった。
展示を見に行くというより、
誰かの家へ、おじゃましに行くような気持ち。
そして、帰り道にふと、
「行ってよかった」と思える。
そこには、確かにこう書かれていた。
「生きているということ。」











この記事へのコメントはありません。