徳島阿波踊り2025 ― 街全体が踊る、魂を揺さぶる夏祭り
はじめに
2025年8月、私は初めて徳島の阿波踊りを訪れました。観覧したのは
- 8月13日:あわぎん南内町演舞場・第一部
- 8月14日:藍場浜演舞場・第一部
- 8月14日:あわぎん南内町演舞場・第二部
そして演舞場を出れば、町中が鳴り物の音と熱気に包まれ、まるで徳島全体が踊っているようでした。この記事では、阿波踊りの歴史から実際に観た演舞までを紹介しながら、初めての体験で心が震えた瞬間をお伝えします。





阿波踊りとは? ― 400年続く徳島の魂
阿波踊りは、400年以上の歴史を誇る徳島発祥の盆踊りです。起源は1586年、徳島城の完成祝いに遡るとされ、庶民の踊りが町へ広がり、大規模な夏祭りへと発展しました。
最大の魅力は「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」という掛け声。観客も踊り手も隔たりなく“阿呆”として楽しもうという精神が息づき、「観る」祭りでありながら「参加する」祭りでもあるのです。





13日・あわぎん南内町演舞場 第一部 ― 中央席で体感した迫力
この日の出演連は、阿呆連、うしお連、扇連、さゝ連、ほんま連、その他多くの連
- 阿呆連:徳島を代表する名門。力強い男踊りと美しい女踊りが調和し、観客を一瞬で引き込みます。
- うしお連:若さあふれる躍動感。鳴り物のテンポが早く、会場が手拍子で一体化。
- 扇連:女性踊りが扇子を使って描く曲線が優雅。夜空に花が舞うよう。
- さゝ連:しなやかでしっかりとした動き。列の美しさが印象的。
- ほんま連:最後を飾る華。人数も多く、舞台全体を埋め尽くす迫力。
中央席では、太鼓の響きが胸にズシンと響き、踊り手の額の汗まで見える距離。観客も自然に手拍子を合わせ、会場がひとつの大きな渦になっていきました。





















14日・藍場浜演舞場 第一部 ― 全体を俯瞰する美しさ
出演したのは、阿呆連、達粋連、天保連、浮助連、うずき連、その他多くの連
- 阿呆連:名門の存在感は藍場浜でも健在。縦列が波のように揺れる。
- 達粋連:鋭い鳴り物と掛け声でテンポが速く、若さと勢いを象徴。
- 天保連:腰を深く落とした男踊りの重心が迫力満点。
- 浮助連:しなやかな踊りと間合いの巧さで観客を魅了。
- うずき連:女踊りの編笠がきれいに揃い、模様のような列が浮かぶ。
後方席からは、これらの連が織りなす模様全体を見渡せました。列が交差する瞬間には観客からどよめきが起こり、スケールの大きさに思わず息を呑みました。
















14日・あわぎん南内町演舞場 第二部 ― 総おどりの圧巻
この部では、新のんき連、無双連、そして最後に総おどり。
- 新のんき連:のんき節に合わせた軽快な踊り。会場を温める役割を担う。
- 無双連:スピード感ある男踊りと鳴り物の迫力で一気に温度を上げる。
そして21:40過ぎ、いよいよ総おどり。阿波おどり振興協会所属の連が合同で出演し、数百人が一斉に舞台に登場。鳴り物の厚みは倍増し、女踊りの編笠が一斉に前傾して揃う光景はまるで光の帯のよう。後方最前列にいた私は、観客全体の手拍子とともにその波を正面から受け止め、全身が震えるような感覚に包まれました。これこそが阿波踊りのクライマックスです。


























街全体が踊る ― 路上と屋台の熱気
演舞場を出れば、徳島の街中がそのまま舞台。両国本町や新町橋の無料演舞場では、観客と踊り子の距離がゼロ。商店街では飛び入り参加型の“にわか連”が盛り上がり、観光客も地元の人も一緒に踊っていました。
屋台からは焼き鳥やすだちドリンクの香り。夜空には提灯が揺れ、川沿いには歓声が響く。**「徳島全体がひとつの祭り会場」**というスケールを体で感じました。





初めて体験して思ったこと
阿波踊りは、単なる観光イベントではなく、徳島の人々の誇りであり、街全体が共有する文化でした。中央席では迫力、後方席では構成美、そして町中では自由さ。それぞれ異なる視点から楽しめる多層的な魅力があります。
「観客」もまた「参加者」となり、自然と手拍子を打ち、声を合わせてしまう。まさに“同じ阿呆なら踊らにゃ損損”を体現する祭りでした。




まとめ
徳島阿波踊り2025は、私にとって人生で忘れられない体験になりました。
400年の歴史を持ちながら、今も人々を巻き込み進化し続ける文化。演舞場の迫力、総おどりの圧巻、そして町全体の熱気。すべてが一つになって、「徳島そのものが踊っている」と感じました。
次は観客としてではなく、踊り手としてあの渦に飛び込みたい。そう強く思わせてくれる、魂を揺さぶる夏祭りでした。







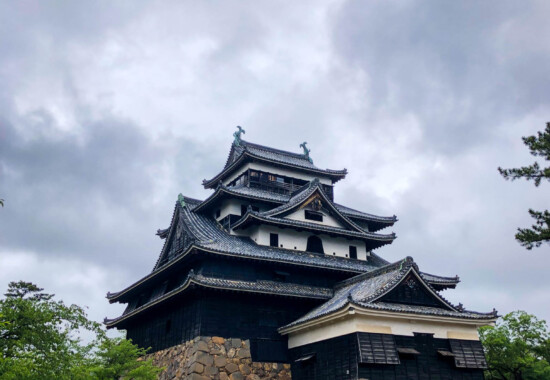

この記事へのコメントはありません。